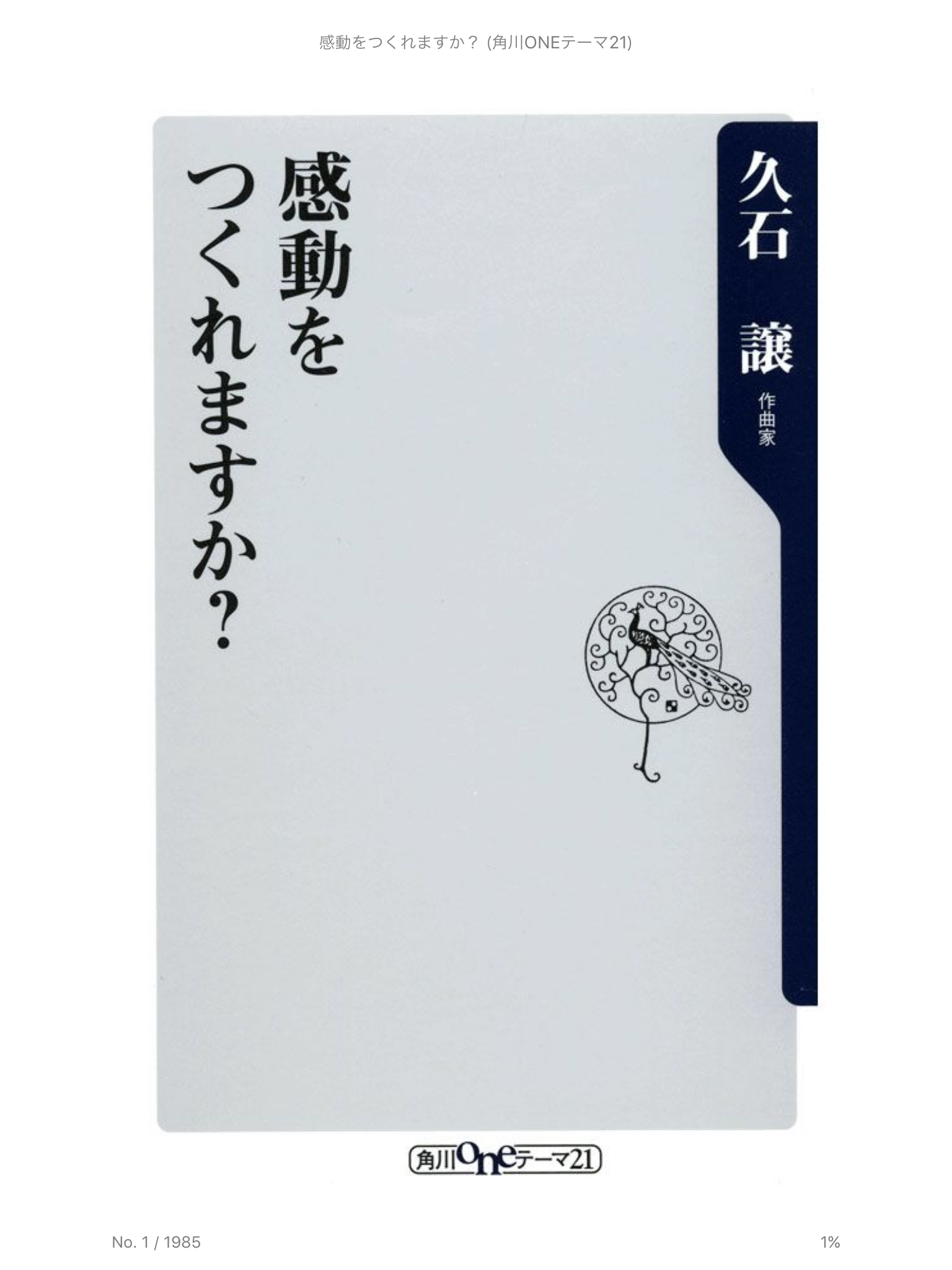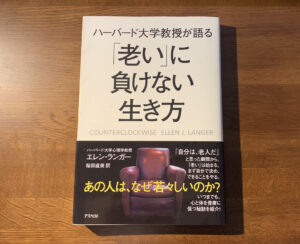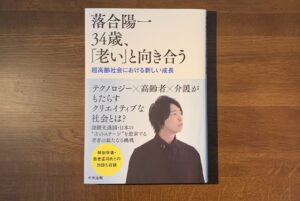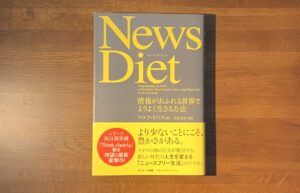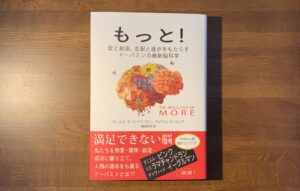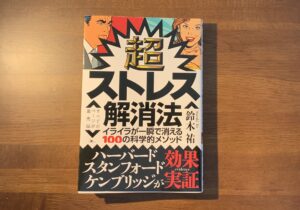今回はジブリ作品の作曲家として著名な久石譲さんの「感動をつくれますか?」のまとめ記事になります。この本は数年前に買ったのですが、ずっと積ん読状態でした。今回一気に読んでみたら、この本にこめられた作曲への情熱とこの本が持つ情報量に圧倒されました。そして作曲以外でも通じるクリエイティブに関してのヒントが満載でした。前半はクリエイティブ全般に関わる話、後半はより個別具体的に映画と音楽についての話が詳細に書かれています。私もかつて作曲家を夢見て全力で音楽に没頭していた時期があったので、今この本を読んで身が引き締まる思いがしました。この記事ではクリエイティブ全般にも応用できる話を中心にまとめていきます。
◆書誌情報
「感動をつくれますか?」
久石譲
角川書店 角川e文庫
電子版 2007/11/1
目次(Contents)
もの作りにおける感性と姿勢についての話。
久石さんも本の中で述べていますが、この本は「創造力とは何か」「感性とは何か」といった問題を言語化した試みです。久石さんの本業である作曲活動は他の仕事と同じように、ある目的のために最良の結果を出すべく最大限の努力をすることです。どんな分野の仕事でもいい意味で予想を覆すアイデアやセンスを要求されているのです。
ものづくりの基本は感性だとよくいう。感性も創造も言葉では説明しにくい。だが、人間はものを考えるという行為を言葉を介してやっている。ということは、僕が音楽家としてやっている方法、視点、もっと無意識下の感覚、そういうものをできるだけ言葉で表現することで、透けて見えるものがあるのではないか。
ものづくりの姿勢には2種類あるとのこと。本書の中では2種類のタイプの名前を明確にしてはいませんが、ここでは本書の内容から判断して「芸術家・アーティスト的な生き方」と「会社員的生き方」の二つに便宜的に名付けることにします。
・「芸術家・アーティスト的な生き方」:自分の作品への想いを主体にして、自分のつくりたいものを作る姿勢のこと。自分自身が満足できるものを求め、一つの作品を仕上げるまでに果てしなく長い時間を費やすこともある。評価軸は自分。
・「会社員的生き方」:社会の一員として自分を位置づけてものづくりをしていく姿勢のこと。世の中の需要と供給を意識し、今自分は何が求められているのかを考え、商業ベースに活躍していく。評価軸は世の中。
クリエイティブの評価軸を自分に置くのか、世の中に置くのかによって2つの姿勢に分かれます。私はこの二つの姿勢の話を読んでサウンドクリエイターの夢を叶えた友人の話を思い出しました。彼は音大時代に多くの「作曲家志望だけど社会に出れない人」「音楽で食えないと嘆いている人」をみてきたそうです。原因はそれらの人たちが前者の「芸術家・アーティスト的な生き方」に固執してしまい、アーティストとしてデビューすることに執着してしまうからだそうです。アーティストとしてメジャーデビューを目指したり、自分の求めるものを追求することにこだわって成功を目指すのは努力だけでは難しい道で(運や時代の流れも必要)、挫折する人も多く「そりゃ音楽で食えなくなるよ」とのことでした。一方、後者の音楽を職能・職人として位置づけ、世の中に求められる音楽を作っていく姿勢・技術を持てばその需要は多く、少なくとも音楽で食っていけないということはないそうです。
久石さんは30歳ごろまで現代音楽の中でも前衛音楽、その中でも同じ音型やパターンを繰り返すミニマルミュージックを追究していたのですが、作家生活の中でもっと世の中に理解が得られる音楽をつくる方向にシフトしたそうです。
音楽大学を出て十年ほど続けているうちに閉塞感を覚え、自分が音楽をやる意味をあらためて考えるようになった。なぜなら、前衛芸術として自分の音楽的実験を正当化するためにどう音楽的に理論証明をするか、他の人の論理を言葉でどう言い負かすか、ということが日常になってしまったからだ。それは僕にとって、もう音楽とはいえなかった。
久石さんは芸術として音楽をする道を捨て、できるだけ多くの人に聴いてもらう幅の広い音楽をつくるような街中の音楽家になろうとこのとき決意したそうです。これは音楽の話ですが、私の経験では美術の世界でもこうしたことが起こっている感じはありますね。
ものづくりを仕事にすることは継続力。気分の波に流されないこと。
クリエイティブを職業として行っていく上で、最も重要なことはなんでしょうか。久石さんは、作曲家として最も重要なことは「とにかく曲を書きつづけること」だと断言します。完成度の高い良い音楽を書くのは大事で、その上で人に喜んでもらえれば作家としてこの上なく嬉しいことです。しかし、ものをつくることを職業としてやっていくためには1つや2ついいものが出来るだけでは駄目なのだそうです。生涯に一作でいいのであれば誰でもいい曲が作れると久石さんは言います。仕事は点では無く線なのです。集中して考え創作する作業をコンスタントに続けられるかどうか。それができてはじめて作曲家、小説家、映画監督と名乗れるのです。
優れたプロとは継続して自分の表現をしていける人なのです。いかに継続して実力が出せるか。常に安定してクオリティの高いものを作り続けられるか。これは私も痛感することなのですが、プロのクリエイターといえども、人間である以上当然気分の波もあります。久石さんは気分の波に揺られること無く創作活動を生活のリズムに組み込むことの重要性を論じています。
何かを表現していく人間にとって、自分の拠り所を気分に置いてしまうのは危ういことだ。
気分は感性の主軸ではないのです(音楽家・アーティストに麻薬に手を出す人が多いのは、この感性の主軸を気分に置いていることが原因とのこと)。そして気分の波に揺るがされないような環境作りが何よりも重要です。久石さんは生活に一定のペースを保ち、できるだけ規則的に淡々と過ごすように心がけているとのこと。今日は気分が乗らないから書けない、などと自分を甘やかすことは出来ず、気分が乗らなくても、調子が悪くてもノルマを達成できるように進めていくことが大事なのです。一時的に徹夜してぶっ通しで頑張りすぎたりして過度な負担をかけると翌日の作業効率が確実に落ちてしまうため、長距離を走り抜くことを念頭に毎日のペース配分を組むのが重要とのこと。
誰のための曲作りか。
また、本の中で久石さんは誰かに気に入ってもらおうと思って曲をつくったことはないとのことを書いています。
人に喜んでもらう、人のためになる音楽をつくりたい、とは思うが、人の評価を意識してつくるということではない。このところをわかってもらうのがわりと難しい。
曲を書く際に「人を感動させよう」とか「美しいメロディーを書いて泣かせてやろう」と考えていることはなく、聴く人がどう受け止めるかは聴く人の自由にしているそうです。結果として作品を送り出して観客が喜んでくれたら「これを作って本当によかった」ということになるだけで、最初から意図的に監督や観客に気に入ってもらうことを意識してつくることは無いと断言しています。
人々の求めるニーズに無関係であってはいけない、かといってニーズに迎合してもいけないのだと思う。
絵と音楽の対比
次に、同じ芸術分野の絵と音楽の比較の話です。芸術には音楽や文学、映画のような時間の経過で成り立つ分野があり、それらは共通した論理構造を持つとのこと。それに対して時間経過を必要としない絵画や美術の分野は作品が表現するものが見た瞬間に分かるようになっており、瞬時に世界を表現できる力があるとのことです。絵は時間の経過を伴わない分、論理的なものより感覚に直に訴えるため、絵の人は考え方や行動においても感覚的な側面が特出するらしい…です。よくある「芸術家は奇人変人が多いというイメージ」は音楽家よりも画家とか視覚芸術家に多いのでは?という話でした(実際本当かどうかは分からないが、今度意識して見ると面白いかもしれないですね)。
そもそも感性とはなにか
次に「感性」の話です。日本人は感性を漠然としたイメージとして捉え、言葉としての「感性」を大事にしすぎていると久石さんは言います。これは感性という言葉ばかりが曖昧模糊なままフワフワしており、それを言語化して切り込んだことはされていないということでしょう。ではそんな感性の実態とはなんでしょうか。久石さん曰く、感性はその人のバックボーンにあるものが基盤となっているのだといいます。
作家としては、いつも自分で新しい発想をして、自分の力で創作しているという意識でやっている。しかし実際には、僕が作る曲は、僕の過去の経験、知識、今までに出会い聴いてきた音楽、作曲家としてやってくることで手に入った方法、考えたこと、それらの蓄積などが基になって生まれてくるものだ。さまざまなかたちで自分の中に培われてきたものがあるからこそ、今のような創作活動ができているわけだ。
「自分独自の感覚だけでゼロからすべてを創造するなんてことはあり得ない。漠然とした感性で創造をしているわけではない。」と久石さんは断言します。作曲には論理的な思考と感覚的なひらめきを必要とし、論理的思考の基となるのが自分の中の知識だったり体験の集積だったりするのです。何を学び何を体験して自分の血肉としてきたかが感性の95%くらいを占めるのでは、と久石さんは考察していきます。
つまり、誰もが感性の基盤となるその積み重ねとその背景にある論理性について思考していけば、ある程度のレベルに達する物はいつでも出来るようになり、それこそが気分に左右されず、仕事としてコンスタントにそれなりの成果を上げられる理由であるといいます。
しかし、問題はその集積さえあればものづくりができるというわけではないこと。95%から外れた残り5%のなかにあるセンスや感覚的ひらめきこそが創造力の肝であると久石さんは指摘します。
ものづくりにおいて直感の果たす役割は大きい。こっちにいったら面白いものができそうだ、という方向性は直感から得られる。けれどその直感も自分の過去の積み重ねからきている。すべてを頭で考えて理性で作っても人の心に響く音楽は出来ない。何か自分でこうしてやろう、という意図的な意識が外れたときに人を感動させるような力を持った音楽が生まれてくる。<抄録>
最後の意図的な意識が外れたときに人を感動させる音楽が生まれてくる、というのが面白いですね。以前私も記事にまとめたフロー状態と通じる部分があると思います。私は音楽、作曲の面白いところはこの論理性と直感で作り上げる過程にあると思います。久石さんは「迷路の中で音を見つける悦びこそが音楽家として最高の悦び」と、よい曲が閃いたときのことを表現しています。
作っている音楽が確信に変わる瞬間がある。「よし!」と思える瞬間、「飛び越えた」といえる瞬間、腑に落ちる瞬間だ。この確信に至るまでは苦しいが、ひたすら考えて自分を極限まで追い詰めていくことで何かが振ってくるのだという。一度閃いてしまえば、一気にクリアになり集中して突き進んでいける。<抄録>
創作の中で確信に変わる瞬間や空気をつかむ瞬間は感じ取るしかなく、努力をして手に入れるような具体的正解があるものでもないとのこと。最後は直感なのです。感性とは直感を鍛えることなのです。
直感を磨くには質より量でたくさんのものを自分の中に取り込む。
では直感を鍛えるにはどうしたらいいのでしょうか?そのヒントは、いかに多くのものを観て、聴いて、読んでいるかが重要とのこと。創造力の源である感性は自分の中の知識や経験の蓄積であり、その絶対量を増やしていくことが自分のキャパシティ(受容力)を広げることにつながるのです。
(映画の話で)「あの映画みた?」と聴かれて「まだ観ていないんだ」ってなるとそれだけでその会話に入っていけない。相手はその映画を引き合いに出してクリエイティブな話をしようとしているのかもしれないのに。
さまざまなところにアンテナを張り、経験を増やしていく。そうした経験から何かを感じ取る感度を磨くことが重要なのです。
コップを観て花瓶といえる感性を持つ。
ものをつくる人間にとって本質的な部分とはなんでしょうか。本書の中で久石さんは「作家は何かを観るときに人と考え方や観点が違うから、絵なり音楽なりで表現したくなる。」と述べています。これは作家は普通の人と同じ見方をしていてはいけないとのことです。コップを見てコップであることを認識していながら、あえてこれは「花瓶です」といってしまえるセンスを持つことが物作りをする人間の本質的な部分なのです。
私はこれを読んで、トイレにサインを書いてアート作品として発表したデュシャンの「泉」の作品を連想しました(参考外部リンク)。
音楽・作曲のヒントとなる部分
久石さんは作曲を本業としているので、音楽を専門的にするにあたってヒントとなる部分も多いです。ちょっと音楽の専門的な話になるので、ここでは簡潔にまとめてみました。
・音の配置のバランスで作曲者の人格(キャラクター)まで分かる。
・一番いい音は無駄のない音で必然性があること。一瞬弾くのをやめただけでオーケストラのバランスが崩れるぐらい厳しいスコアであればあるほど音楽として最高。
・無駄な音が多いと、着ぶくれしたおじさんみたいな譜面になる。
・クラシック音楽の良さは譜面で様々な着想のヒントを得られること。バルトークは論理的で厳格な音の構成を持つため、感情(エモーション)の入り込む余地は無く、ショパンやラフマニノフは音の厳格さよりもより感情的な部分への比重が大きい。
多くの映画音楽に携わった久石さんだからこそ言える映画音楽づくりの学び得たこともまとめておきます。
・この映像に合う音楽を作ろう、この作品が必要とする音楽を書こう、と考える。監督もこの映画の世界に合うか合わないかという視点で捉えているはずだから。
・その仕事、その映画にとって必要なものをきちんと提供することが大切。
・メインテーマが一番重要。
・ハリウッドは人物に音楽をつける。
・冒頭5分の扱いでその映画全体の音楽の量/世界観が決まる。
・映画と音楽の構造は非常によく似ている。
・クラシックのオペラ作曲家は現代に生きていたら映画音楽の仕事をしていただろう。
映画音楽について、映画はフィクションであり過剰な状況説明をしてしまいがちになるのが問題点だと指摘しています。そうした音楽は観る側に想像の余地を残さない、言い換えれば作り手の感情をもろにぶつけるような押しつけがましい音楽は聴く人のイメージを限定してしまうので、それ以上の感情を引き出すことができないのです。音楽の持つ役割をきちんと考えずに容易につけると、映画全体を安っぽくしてしまうとのこと。
映画音楽を構成する状況外音楽と状況内音楽
専門的な映画音楽の話です。映像の背後に音楽が流れるのは本来不自然なもの。映画を盛り上げていくための音楽を「状況外音楽」といいます。できるだけ現実に即した形だと音楽はほとんど入ることは無く、BGMは映画の一場面で喫茶店の店内BGMとか登場人物が楽器や歌を歌うときの限定された場面になります。こうした自然の流れの音楽は「状況内音楽」といいます。映画音楽は「状況外」と「状況内」の二つを示し、一般的には状況外音楽を指し、後者は効果音のように捉えられています。
久石さんは音楽が映像の従属物になってはいけないとして、ロマンチックなシーンに甘い音楽といういかにもなパターンは音楽が映像に寄りかかっていることを指摘しています。悲しいシーンに切ない音楽、嬉しいシーンに明るい音楽をつけるのではなく、あえて異なる印象の音楽をつけることで状況を際立たせる手法を「対位法」といいます。黒澤明監督の「野良犬」には非常に効果的に対位法が使われているとのこと。映画では音楽がシーンの雰囲気「アトモスフィア」(雰囲気とは場の空気に含まれる陰影のようなもの)を高める効果を持つとのこと。
最初の聴衆は自分自身
久石さんは自分の曲の最初の聴衆は自分だからこそ、自分が興奮できないようなものではダメだといいます。まずは自分を喜ばせる曲を作ること。これは音楽に限らず、どの創作活動でも同じではないでしょうか。恥ずかしいという感情は自分をよく見せたいと思う心の裏返しであり、自分をさらけ出すことを恐れていることです。頭の中にそんな自意識があると、本当に人を楽しませたり喜ばせたりするものをつくることはできないとのこと。
経験についての話では、経験たくさん積むことは大切だが、経験は人を臆病にする面もあることを指摘しています。自分の新しいチャレンジにに水を差すような経験であれば、その人にとってその経験はプラスとはならず、進歩を妨げるものでしかないのです。うまくいかなかった原因を理解し、今度はそういうことがないようにするのが経験を活かすということです。プラスに生かせない経験であれば、豊富にならないほうがよいのです。
人間苦労は買ってでもしろというが、出来ることなら苦労はしない方がよい。苦労は偉いことだと持ち上げる人は大抵苦労自慢をし、結局いいたいのはそんな自分がどれだけ頑張ってここまでになったか、という自慢でしかない。楽な人生は無く、みんな人知れず苦労しているのであるから、自分から進んで苦労する必要は無い。苦労自慢する人は知性が感じられない。<抄録>
と苦労自慢をしている人をバッサリと切っているところが痛快でした。
普通の苦労は人間の幅を広げない。幅を広げるには知性を磨くことと、本当の修羅場をくぐり抜けること。
私も10代の頃から相当苦労してきましたが、無駄な苦労はしない方がいいとずっと思ってきているのですごく共感しました。経験が足かせになって俺はもう年だから、とチャレンジしない人がなんと周りに多いことか…。
その他本書で気づきを得られたこと
最後に本書で学べたことを簡単にリストでまとめます。
・クラシックが量産できたのは明確に形式(フォーマット)が決まっていたから。
・音楽家にはっきりとした作家性が見られるようになったのはベートーヴェンの功績。それまではクラシック音楽は貴族のものだった。
・作家性を強く出していく流れの中でロマン派が生まれ、感情的要素を取り入れられた。演劇のように音楽を構成する交響詩という形式はロマン派音楽の台頭から生まれた。
・決まり切った形式から脱出しようとして舞台の劇的な要素を音楽に取り入れようとした。
・ポップスはリズムで世界を制した。クラシック音楽は複雑化の流れに向かいリズムを失って理論が肥大化していったが、ポップスは分かりやすいメロディとリズムとを前面に出すことで人々の生活に必要とされる音楽になった。アフリカ奴隷が海を渡り、彼らの持つ強烈なリズム感がジャズへと発展したことが20世紀はポップスの時代の基礎となった。
・30歳を過ぎてから演奏者としてピアノを弾く訓練を始めた。作曲家久石譲の創作の意図を誰よりもよく理解しているのは他ならぬ自分自身だからである。
・ポップスでわかりやすく親しみやすい音楽をつくるということは、突き詰めていくといいメロディを書いて、心地よいリズムとしゃれた和音をどうつけるかということになる。それだけでは作曲家としてはつまらないので、色々試したくなるが、親しみやすい音楽ではなくなってしまう葛藤がある。
・伝統楽器は癖が強く、主張が強いため使いにくい。
・日本は古き伝統をそのまま守っていくことが得意。中国は自分なりのアレンジで伝統を時代に合うように変化させていく。
・うまさよりも「何を伝えたいか」が大事。ピッチとリズムを超えた伝えたいこと。スコアとしての完成度よりも、何を伝えたいか。
宮崎さんが「(その映画を見終わったら)1階から入った人が2階から出てくるような感じになるといい」といっていたことがあった。僕も同感で、勇気が出たとか、一つ賢くなったとか、何かプラス材料になるものを得てほしいという願望がある。(中略)そのためには音楽も、観る人の脳細胞が活性化するようなものでありたい。観客のイマジネーションの入り込む余地を持たせた映画音楽を、僕はつくりたいのである。
満足度95%
満足度は95%、物作りをするに当たって多くのことを学ぶことが出来ました。ボリューム満点で、後半はより作曲家としての具体的な映画と音楽の話が続きます。一番印象に残ったのが「いかに継続して実力を発揮できるか」の話です。継続して事を成すことの難しさについて多くを学べました。音楽について知りたい方はもちろんのこと、映画音楽やサウンドクリエイター、作曲家を目指す人、高みを目指す全クリエイター必読の書だと思います。私の方でも記事として多くの箇所をまとめてみましたが、興味があれば是非手に取って読んでみて欲しい本です。